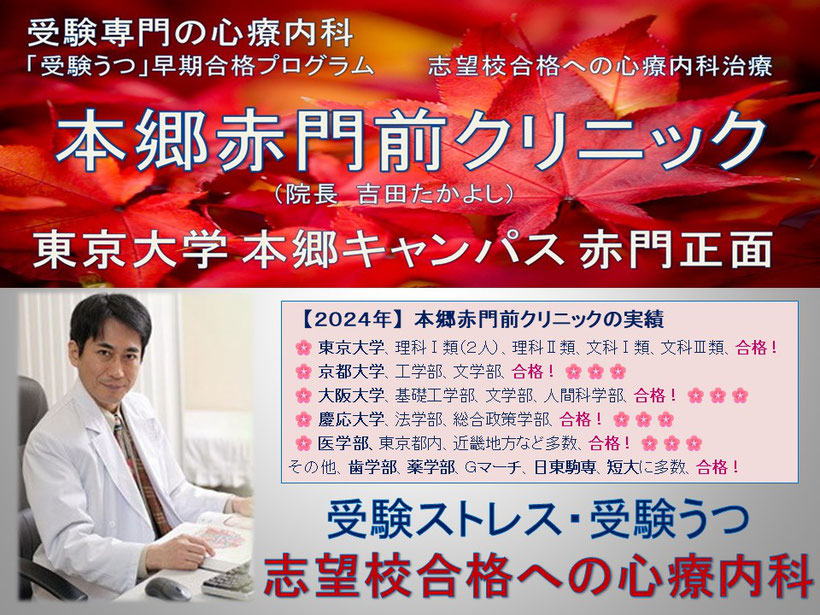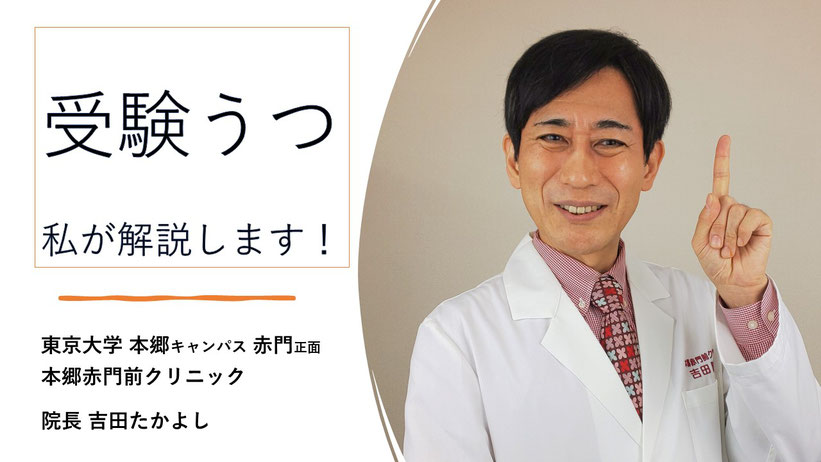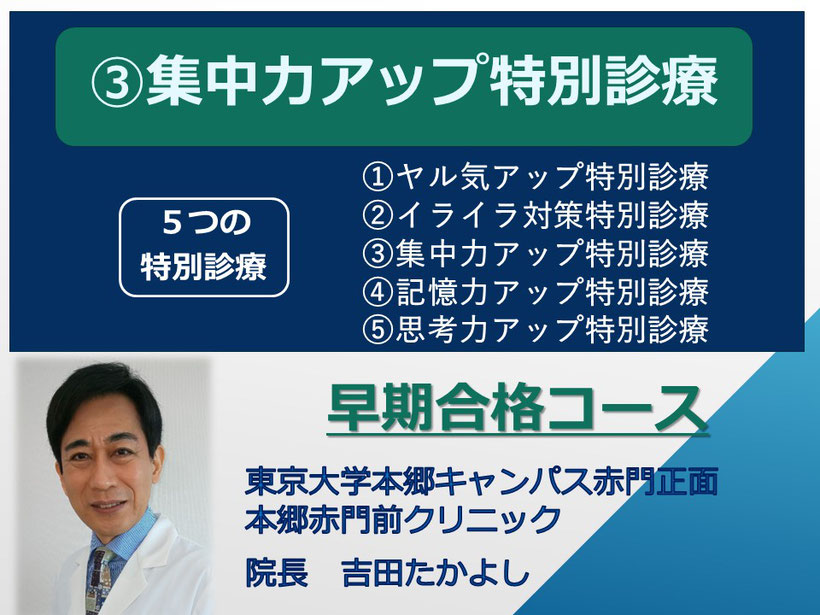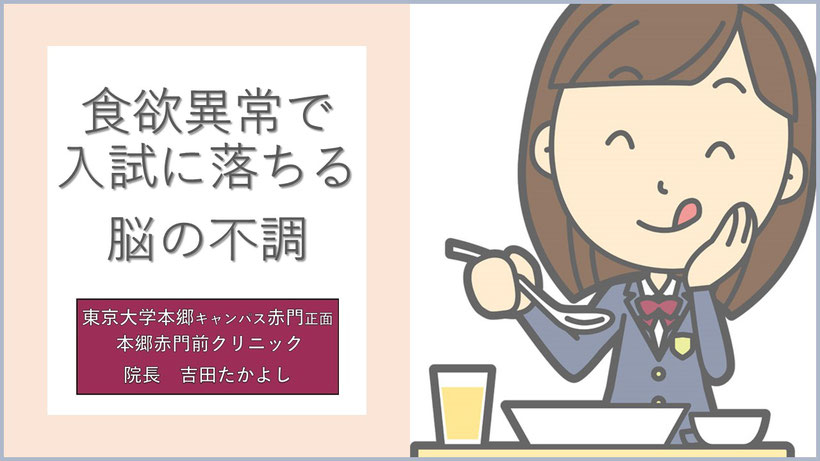
受験生の食欲の異常
Exam stress Eating disorder
入試に落ちる脳のSOSサイン
「合格するための食事の6か条」とは?
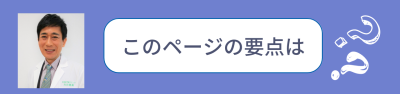
✓ 受験ストレスによる食欲の異常(Exam stress Eating disorder)が受験生の間で増加しています。これが脳の認知機能に波及し、入試の結果に深刻な影響を与えます。
✓ 食欲がなくなる場合と、逆に、とめどなく食べすぎてしまう場合の両方があります。いずれも危険な脳のSOSサインです。放置しておくと、思考力や集中力の低下を招き、入試の当日に大きな得点力ダウンにつながります。
✓ 一見、関係がないように感じる食欲の異常と集中力や思考力の低下が連動して起こる理由は、脳の中にある視床下部(hypothalamus)という部分が、食欲の中枢とストレスの中枢の両方の機能を兼ねているためです。
✓ 食事のときに、ちょっとしたことを心がけるだけで、食欲の異常は大幅に改善します。その方法として、誰でも今日から実践できる「合格するための食事の6か条」をご紹介します。
✓ 脳のコンディションを最適な状態に引き上げることによって、現在の成績よりも偏差値の高い志望校への合格も可能になります。その方法もご紹介します。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

受験ストレスによる食欲の異常とは?
お腹が減るのに食欲がわかない・・・。
「オエッ!オエッ!」っとエズイてしまう・・・。
逆に、食べても食べても満腹にならず、とめどなく食事を続けていまう・・・。
「スリムで、カワイイね!」といわれていたのに、気がつけばおデブちゃんに・・・。
あなたには、そんな症状が出ていませんか?
これは、受験ストレスによる食欲の異常(Exam stress Eating disorder)が原因です。
今、女子の受験生を中心に、こうした症状が増加しており、さらに増加のペースに拍車がかかっています。
「受験で頭がいっぱいなので、食欲なんてどうでもいい・・・。」
そう考えて、放置する方も多いようですが、これはダメです。
食欲の異常は、受験ストレスによる脳のSOSサインです。
放置していると、メンタル面の不調から脳機能の低下をもたらし、やがて入試の問題が解けなくなってしまいます。
特に、プレッシャーがかかる入試の真っ最中に、脳の機能に乱れが生じ、集中力を保てなくなりやすいという事がわかってきました。
つまり、努力しても入試に落ちてしまう脳になってしまう危険性があるということです。
志望校合格を勝ち取るためには、どうして食欲の異常(Eating disorder)が現れるのか、脳科学とメンタル医学のメカニズムを理解した上で、正しい対策が不可欠です。

受験ストレスで食欲の異常をもたらす脳の視床下部(hypothalamus)
脳科学の視点で見ると、受験ストレスが食欲の異常をもたらすのは、必然の結果です。
受験ストレスの症状は、最終的には、脳の奥深くにある「視床下部(hypothalamus)」という部分が中心になって生み出します。
実は、食欲を管理する中枢も、まったく同じ「視床下部」にあるのです。
人間の巨大な脳の中で、「視床下部」は、オリーブの実と同じくらいの小さなものです。
ですから、受験ストレスと食欲の異常が連動するのは、解剖学的にも必然的に起こる現象だといえるわけです。
受験ストレスによって「視床下部(hypothalamus)」の機能が異常をきたすと、食欲がなくなる場合と、食欲が高まりすぎる場合と、どちらのケースも起こりうることです。
食欲が旺盛だったら健康だと思い込んでいる人が多いのですが、過食になってしまうのも脳の異常によるものだということは、頭に入れておいてください。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

よく噛めば視床下部がリセット!
受験ストレスによる食欲の異常(Exam stress Eating disorder)に気づいたら、真っ先に行っていただきたいのは、食事中、とにかく、よく噛むように心がけること。
噛むことによって、脳に刺激が送られ、視床下部がバランス良く働くようになる作用があるのです。
食欲の不振が、噛むことによって緩和されるということは、どなたもイメージがつくと思います。
しかし、注目していただきたいのは、過食の場合も、噛むことによって、症状が収まる効果があるということです。
受験ストレスによって視床下部にある満腹中枢が働きにくくなることによって過食がおきますが、よく噛むと、満腹中枢の回復を促してくれる作用があるのです。
軽症の場合は、これだけで治ることも珍しくありません。
目安は、食べ物を飲み込むまでに20回、噛むことです。
本当のことを言うと、医学的には、30回、噛んでから飲み込むのが理想的だとされています。
ですが、これは現実にはかなり大変です。
まずは、20回を目標にするといいでしょう。

試験当日は朝食に時間をかけよう!
受験生にとって、食事のときによく噛むことによるメリットは、視床下部(hypothalamus)の働きを回復させるだけではありません。
脳の認知機能を高め、入試などの問題を解く能力も高める作用もあることが、実験結果として証明されているのです。
脳のメインスイッチの役割を担っているのは、主に、脳幹網様体(reticular formation)と呼ばれる構造体です。
この部分が、噛む回数が増えることによって刺激を受けるため、脳の認知機能の働きがアップするわけです。
こうした効果は、昼食でも夕食でも現れますが、とりわけ効果が高いのが朝食なのです。
ですから、特に試験の当日は、普段よりも朝食に時間をかけ、しっかり噛むように心がけると、得点力のアップに効果があります。
また、消化が良くなるため、胃の負担が軽くなり、その分だけ脳に送られる血液も増加します。
まさに、二重三重にメリットがあるわけです。
受験生は、普段から、朝、少しだけ早起きをして、朝食をよく噛んで食べる練習をしておきましょう。
私はこれを「朝食トレーニング」と呼んでいます。
受験生は忙しいから無理だと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
本郷赤門前クリニックが学習塾と共同で調査を行ったところ、平均すると、それまでの朝食の時間に、たった5分追加するだけで、20回噛むことが実践できるというデータが得られています。
また、以下の「合格するための食事の6か条」も、それぞれ医学研究で効果が実証されています。
ぜひ、可能な範囲で実践してください。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

合格するための食事の6か条
【合格するための食事の6か条】
その1:食べ物の香りをよく嗅いでから食べる。
食事の香りが脳の視床下部に働きかけ、受験ストレスを緩和させる効果があります。
また、食べ物を飲み込む前に、香りを嗅ぐことによって胃腸の働きが整えられます。
それが脳腸相関と呼ばれる現象を通して、脳機能の働きも連動して高めてくれる効果が生じます。
その2:食べ物をよく見てから食べる。
食べる前に、これから口に入れる食べ物をよく見ておいたほうが、食事によるストレス緩和作用が大きくなることも実証されています。
また、香りの効果と同じように、視覚的にも脳に食べ物をしっかり認識させた方が、胃腸の働きがよくなることで脳の認知機能にも、良い効果が生じます。
その3:テレビやスマホを見ながら食べる「ながら食べ」はしない。
「ながら食べ」をすると、食べ物を見る時間が減り、上記の効果が得られなくなります。
また、食べているという自覚が希薄になり、結果的に過食を助長する原因になります。
あるいは逆に、胃腸の受け入れ体制が整わないために、機能性ディスペプシアなどの胃腸の不調を招いて食欲不振を悪化させる原因にもなります。
その4:家族と会話をしながら食べる。
食事中に会話をすると、視床下部にある摂食中枢や満腹中枢の機能が正常化する効果が生じることが、実験データとして実証されています。
会話にはストレス緩和作用があり、これによって視床下部の働きがよくなることが原因です。
親しい友人との会話でもこの効果は生じますが、家族との会話は、特に効果が大きいことがわかっています。
その5:食卓の照明を波長の長い光(電球色:オレンジ色っぽい光)にする。
目の網膜が波長の長い光を感じると、食欲の中枢がバランス良く働くことが証明されています。
このため、食事中の照明は、波長の短い青白い光ではなく、波長の長いオレンジ色っぽい光のほうが望ましいわけです。
同じ食べ物であっても、波長の長い光で照らしたほうがおいしく感じるという実験データが得られていますが、これは脳の視床下部の性質によるものです。
その6:食事中は受験のことを考えない。
ストレス源となる悩みについて考えるだけで、胃の動きや消化液を分泌する能力が一瞬にして低下してしまいます。
食事のときだけは受験のことを考えないように心がけることが、逆に、受験の結果を良くする効果を持っているわけです。
特に緊張が高まる入試の直前期には、食卓での受験にかかわる話はすべて禁句にしましょう。
入試が終わった後に出かける旅行やレジャーなど、楽しい話がおすすめです。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

食欲の異常は「受験うつ」のSOSサイン!
もし、上記の6か条をいくつか実践しても、受験生の食欲の異常が改善しない場合は、軽く考えないでいただきたいです。
単なる受験ストレスの問題ではなく、脳が「受験うつ(Exam Depression)」の段階に進行している可能性があるためです。
また、神経性大食症(Bulimia nervosa)、神経性無食欲症(Anorexia nervosa)、機能性ディスペプシア(Functional dyspepsia)などの病気になっている場合もあります。
これらの場合は、専門の治療が必要です。
3日間、合格するための食事の6か条を実践しても改善しない場合は、決して放置してはいけません。
いくら勉強しても合格できない脳の状態になってしまうという悲劇が待ち構えているかもしれません。
それどころか、症状が悪化して、人生を棒に振ってしまうリスクもあるのです。
特に「受験うつ」は、世間の人が考えるうつ病のイメージとはかなり異なります。
そのため、「食べすぎなんて、受験うつとは関係ない」と、決めつけてしまう受験生や親御様が少なくありません。
しかし、近年、食欲の異常だけが症状の前面に出る「食欲異常型の受験うつ」が増加しています。
この場合は、放置してしまうと、やがてイライラしやすい脳になり、集中力の低下や思考力の低下が生じます。
「食欲異常型の受験うつ」を見逃すことにより、対策が手遅れになって、多くの方が入試に落ちてしまっているのが現実です。
「受験うつ」がどのようなものなのか、ぜひ、以下の「受験うつ」のページもご覧いただければと思います。
東京大学 本郷キャンパス 赤門正面
本郷赤門前クリニック

志望校への合格をもたらす脳の検査とは?
食欲の異常が続く場合、まず、脳の中で何が起こっているのかを正確に把握することが、志望校への合格を勝ち取るために、決定的に重要です。
そのために、とても役立つのが「受験に特化した光トポグラフィー検査」です。
人体にまったく無害な近赤外線という波長の光を利用することで、脳のどの部位がどのように働いているか、手にとるようにわかるのです。
そのため、過食や食欲不振が「食欲異常型の受験うつ」に進展しているのかどうかを見極めるためにも、とても効果的な検査方法なのです。
また、このデータと認知機能の検査のデータを組み合わせると、志望校の合格のために何をどうすべきかが浮き彫りになります。
脳医学に基づく勉強法の最適化にも利用できますので、入試のためには、二重三重に役立つ検査だと言えます。
以下をクリックしていただけば、「受験に特化した光トポグラフィー検査」の詳しい解説がご覧いただけます。

志望校への合格をもたらす脳の検査とは?
2020年からは、志望校への合格をより強力にサポートするために、早期合格コースの一部として「5つの特別診療」を開始しました。
以下の5種類の特別診療の中から、受験に特化した光トポグラフィー検査と脳機能についての検査データをもとに、必要なものをチョイスして受けていただきます。

食欲に異常を抱えた受験生の場合は、視床下部の機能不全に起因した集中力の低下が起こっている場合が多く、特に③集中力アップ特別診療がとりわけ効果的です。
また、「①やる気アップ特別診療」、「②イライラ対策特別診療」も必要になる場合が多く見られます。
以下をクリックしていただけば、「5つの特別診療」に関する詳しい案内がご覧いただけます。

参照した研究論文のリスト
① Kandiah, J., Yake, M., & Willett, H. (2008). Effects of Stress on Eating Practices Among Adults. Family and Consumer Sciences Research Journal.
② Ahn, G. (2011). The Effect of Stress Experiences on Abnormal Eating Behavior of Female High School Students. THE KOREAN JOURNAL OF STRESS RESEARCH.
③ Hyldelund, N., Dalgaard, V., Byrne, D., & Andersen, B. (2022). Why Being ‘Stressed’ Is ‘Desserts’ in Reverse—The Effect of Acute Psychosocial Stress on Food Pleasure and Food Choice. Foods.
④ Harris, B., Young, J., & Hughes, B. (1984). Appetite and weight change in patients presenting with depressive illness.. Journal of affective disorders.
⑤ Lee, E., Hanchate, N., Kondoh, K., Tong, A., Kuang, D., Spray, A., Ye, X., & Buck, L. (2019). A psychological stressor conveyed by appetite-linked neurons. Science Advances.
⑥ Simmons, W., Burrows, K., Avery, J., Kerr, K., Bodurka, J., Savage, C., & Drevets, W. (2016). Depression-Related Increases and Decreases in Appetite: Dissociable Patterns of Aberrant Activity in Reward and Interoceptive Neurocircuitry.. The American journal of psychiatry.
⑦ Torres, S., & Nowson, C. (2007). Relationship between stress, eating behavior, and obesity.. Nutrition.
⑧ Baranowska, B., Wolińska-Witort, E., Wasilewska-Dziubińska, E., Roguski, K., Martynska, L., & Chmielowska, M. (2003). The role of neuropeptides in the disturbed control of appetite and hormone secretion in eating disorders.. Neuro endocrinology letters.
⑨ Maxwell, M., & Cole, D. (2009). Weight change and appetite disturbance as symptoms of adolescent depression: toward an integrative biopsychosocial model.. Clinical psychology review.
⑩ Witt, A., & Lowe, M. (2014). Hedonic hunger and binge eating among women with eating disorders.. The International journal of eating disorders.
⑪ Mehrabian, A., & Bernath, M. (1991). Factorial composition of commonly used self-report depression inventories : relationships with basic dimensions of temperament. Journal of Research in Personality.
⑫ Morley, J., Levine, A., & Kneip, J. (1981). Muscimol induced feeding: a model to study the hypothalamic regulation of appetite.. Life sciences.