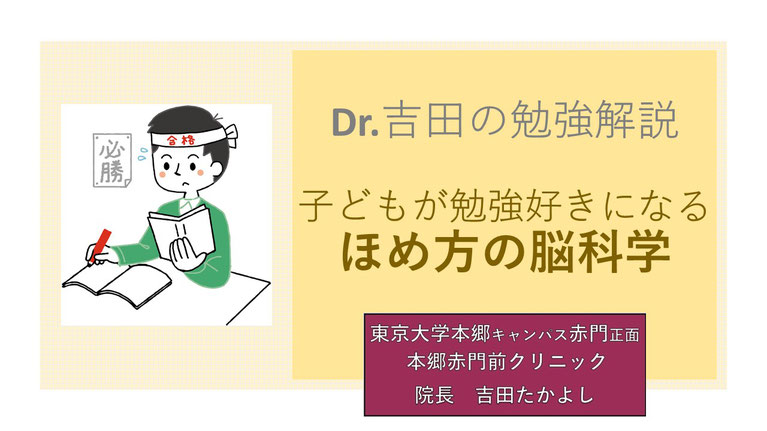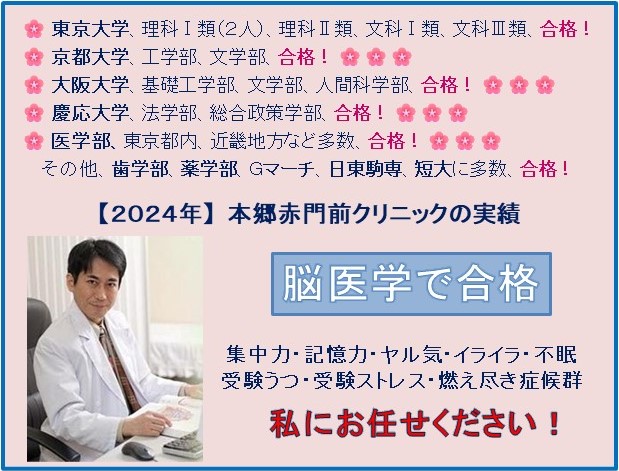解説!Dr.吉田の勉強脳科学!
子どもが勉強好きになるホメ方の脳科学!
【このページの要点】
・「頭がいい」とホメると、努力しない脳に育つ効果が生じます。
・ホメると、脳のA10神経が刺激を受へ、脳の発達を促します。
・A10神経を飽和状態にしないホメ方が、子どもの脳を持続的に育てる作用があります。
・具体的には、子どもの脳を育てるには、「ホメるプラスワン」のテクニックが効果的です。
毎週水曜日に出演させていただいている文化放送の「ドクター吉田のSAKIDORIクリニック」
昨日のテーマは、「子どもが勉強好きになる、ホメ方の脳科学!」
お話した一部を抜粋して、ご紹介します。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック
私のクリニックは、メンタル医学と脳科学を応用して、受験生の無気力や集中力を治して志望校に合格してもらう専門の心療内科なんですね。
それで、親御さんに、脳科学を応用した子どもの褒め方の指導もしているんですよ。
子どもを褒めるのが大事なのは、今や常識ですね。
でも現実には、現代っ子は褒めると増長しちゃうし、かといって叱るとふて腐れることも多い。
そういうのを感じることはありませんか?
私は、ちょうど1年ほど前、この番組で、「頭がいい」と褒めてはいけないというアメリカのコロンビア大学の研究をご紹介しましたね。
持って生まれた才能を褒めると、努力をせずに結果を出す天才でありたいという願望が強くなる。
そして、努力しない子どもに育ってしまう。
逆によく頑張ったと、努力を褒めると、努力が大事だという観念が強くなる。
それで、無意識のうちに努力を繰り返して、結果として学力も高くなるという研究結果だったんですね。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック
でも、褒めて伸ばすには、もう一つ大事な点が、脳科学の研究で見つかったんですよ。
人間は褒められると心地よい気分になりますね。
これは脳の中にあるA10神経が刺激を受け、快感物質のドーパミンを分泌するためなんですね。
スイスのチューリッヒ大学などの研究で明らかになっているんです。
脳は本能的にドーパミンの快感を再現したい欲求を持っている。
だから、本能的に褒められた行為を再現しようとするわけですね。
努力を褒めたら、より努力するようになるというのも、同じです。
A10神経に、もっとドーパミンを分泌させようとするからなんですね。
ケンブリッジ大学が実験を行ったら、A10神経はとても刺激に慣れやすい。
次第にドーパミンを出さなくなるというデータが出たんですね。
これが、現代っ子を褒めるのが難しくなった最大の理由だと指摘されているんですね。
ちょうど20年ほど前から、心理学の研究で、褒めることのプラスの効果が見つかりました。
それで、世界的に子どもを褒めることがもてはやされたんですね。
これって、日本だけじゃないんですよ。
でも、結果として、逆に、子どもの心に響かなくなってきている。
そう、アメリカを中心に多くの先進国で指摘されているんですね。
その原因が褒め言葉に慣れてしまい、脳のA10神経が反応しにくくなったということなんですよ。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック
実は、薬物依存症やアルコール依存症も、同じなんです。
A10神経が慣れてしまうために発病するんです。
だから、脳を快感に慣れさせないことが予防に役立つんですね。
褒め方についても、A10神経を飽和状態にさせないことが、子どもを伸ばす秘訣だと言えるんですよ。
では、具体的には、どうやって子どもを褒めればいいのでしょう。
私は「褒めるプラスワン」のテクニックと名付けて、提唱しているんです。
褒めっぱなしにせず、必ず褒めた後に、ほんの少し叱っておくということです。
たとえば、子どもが試験でいい点数をとったら、「よく頑張ったね」と、まずは褒めるんです。
それで、その後、「でも、ケアレスミスは駄目だね」と、ちょっとだけ叱っておく。
あるいは、「次は、ケアレスミスもなくせば完璧だね」でもいい。
それとなく、次に向けての課題を添えるというのでもいいんです。
これによって、A10神経は飽和状態にならない。
次に残りの課題を克服して褒められたときに、ドーパミンをたっぷり出せる余力が脳に蓄えられる。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック
一方、叱るときも、「プラスワン」のテクニックが効果的なんですね。
今どきの子どもは、叱ると、耳をふさいで、脳をシャットアウトしてしまう。
そうなっちゃうと、何を言っても脳に届かないから、意味がない。
みなさんのご家庭でも、あるんじゃないですかね?
そこで、叱る場合は、必ずその前に、軽く褒めておく。
たとえば、試験でひどい点数をとってきたら、叱りつけたい気持ちを、いったん我慢する。
それで、「最後まで諦めずに頑張ったのはよかった」と、何かプラスの点を見つけて、軽く褒めておくんです。
そうして、子どもの脳が親の話を聞いてもいいなと感じたところで、ガッツリ叱る。
褒めるときのプラスワンは、褒めた後に。
叱るときのプラスワンは、叱る前に。
順番は逆なので、これは間違えないようにしていただきたい。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック
また、褒めるときに、なぜ上手くいったのか、その理由も明確に付け加えるプラスワンも効果的です。
「いい点数をとって偉いね」と理由を示さずに褒めると、子どもの脳は自分が優秀な人間で、これからも無条件に良い点数を取り続けるはずだと感じ取り、未来の成功を先食いする形でA10神経が飽和状態になっちゃう。
頭がいいねと褒めたら努力しなくなるというコロンビア大学の実験と、同じことが起こってしまうわけですね。
でも、「宿題を頑張ってやったから、いい点数が取れたね」と理由を示しながら褒めると、もし宿題をサボったら、次は良い点数を取れないと判断するため、
A10神経の飽和に歯止めがかかります。
その上、ドーパミンの快感を得るには、宿題が不可欠だとハッキリ認識できるので、一石二鳥ですよね。
これも、叱るときも同じで、なぜ、悪い点数になったのか、理由を明確にして叱ると、次は、その対策をしたら再発を防げるから大丈夫だと認識し、落ち込まずに前向きになれますね。
ただし、ここまでご紹介したのは、あくまでもお子さんの脳が本来の健康な働きをしている場合に限った話です。
現代っ子の脳は、ストレス耐性が低く、「受験うつ」や「受験脳疲労障害」など、何らかの不調が起こっていることが多いんです。
この場合は、CBT治療や磁気刺激治療など、専門の治療をしないと、勉強にしっかり取り組むようにはなれません。
私の「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」は、受験生の脳と心の不調を治し、早期に志望校合格を勝ち取るための専門の診療コースです。
メンタルが回復するだけでなく、脳の働きが良くなるので、試験にはとても有利に働くので、それが合格実績に表れています。
親御さんには、隠れたお子さんの脳の不調を見逃さないようにしていただきたいですね。
受験生の脳と心に少しでも不調の兆候が現れたら、ご案内メールをお気軽にご請求ください。少しでも
文化放送「ドクター吉田のSAKIDORIクリニック」より
本郷赤門前クリニック 吉田たかよし院長の解説を抜粋しました。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

ご案内メールの請求と受診のお申し込み