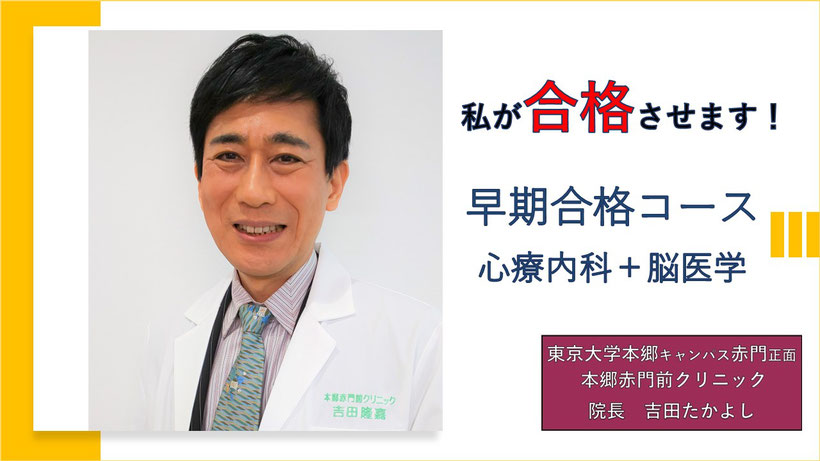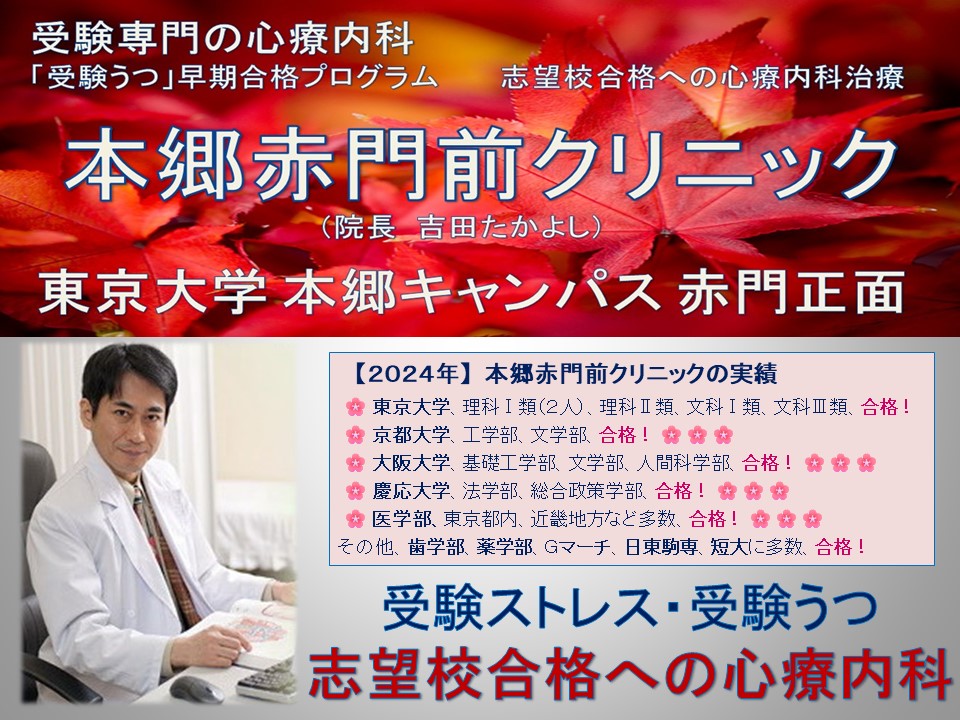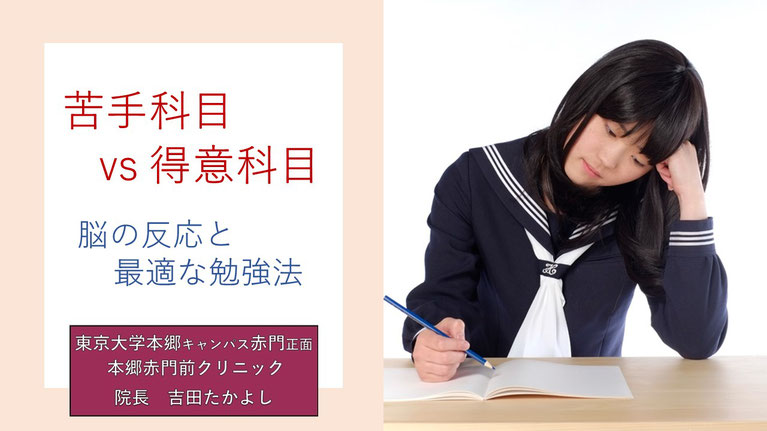
得意科目 vs 苦手科目
脳の反応と最適な勉強法

① 得意科目と苦手科目では、勉強する場合に脳の働き方が根本的に異なることがわかってきました。効率的に勉強するには、それに合わせて勉強のスタイルも変える必要があります。
② 得意科目を勉強する場合は、脳内で「没頭」と呼ばれる現象が起きるため、ある程度は長時間、まとめて勉強したほうが効率がアップする傾向があります。
③ 苦手科目を勉強する場合は、脳の扁桃体が暴走しやすいため、15分程度しか高い集中力を維持できないというデータが出ています。
④ ある科目の勉強をした後で次の科目の勉強に移る場合、異なる脳の領域を使う科目の組み合わせを選べば、脳の過剰な疲労を回避できます。そのため、効率の良い勉強ができるほか、受験ストレスも生じにくくなります。
⑤ 脳の背外側前頭前野の機能を高めると、扁桃体の暴走が収まり、意識が消えるとともに、集中力・記憶力・思考力が高まるため、問題を得能力が飛躍的に高まります。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

脳科学で見つかった苦手科目の克服法!
誰だって、嫌いな科目や苦手な科目はありますよね。
実は、私自身も、社会科が大嫌いでした。
そこで、中学受験では、入試に社会科がない灘中学を受験。
大学受験では、理系だったので、共通一次試験の日本史と政治経済をごまかしごまかし突破。
でも、国家公務員上級経済職試験に上位で合格するには、経済史はもちろん、日本史・世界史・地理、それに文学史や美術史も落とせません。
理系から独学で文系の試験に参戦した私にとっては、これはキツかった・・・。
そこで、このとき、苦手科目の勉強法を苦肉の策で編み出したんです。
受験の脳医学を専門に扱う心療内科医になったあとで分かったことですが、実は、この勉強法が、脳科学的にも、まったく正しいことだったんです。
このページでは、その方法をご紹介します!

苦手脳にピッタリあった「15分勉強法」
よく、嫌いな科目についても、「好きになりなさい!」って叱る親がいるけど、これって、無理な話ですよね。
私は、そんなことは、早々にあきらめました。
それで、仕方なくやるようになったのが、「15分勉強法」
嫌な科目の勉強は、15分たったらやめるという、とってもシンプルな勉強法です。
嫌々やる苦手科目の勉強の場合、経験上、効率が上がるのが、せいぜい15分だったので、当時は結果としてそうなっただけなのです。
でも、そのやり方で文学史以外は、満点をとることができました。
なぜ、うまく行ったのか?
それは、人間の脳機能の仕組みにピッタリあっていたからです。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

好きな科目と嫌いな科目では、脳の働き方が異なる!
実は、好きな科目と嫌いな科目では、脳の働き方が根本的に異なるということがわかってきました。
好きな科目だと、脳では「没頭」と呼ばれる現象が起きます。
この場合、脳は高い機能を長時間にわたって維持できます。
あなたも、好きなことに熱中して、時の流れを忘れてしまったことがあるはずです。
だから、得意科目については、むしろ、長時間、まとめて勉強したほうが効率的なんです。

15分のローテーションが脳の集中力を高める!
でも、嫌いな科目を勉強する場合は、脳の前頭前野という部分を過酷に使って、無理やり脳機能を働かせる必要があります。
だから、集中力を維持するには、15分位が限界なんですね。
もちろん、1日15分だけの勉強では足りません。
だから、いろんな科目や分野をローテーションで、回していくんです。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

理想のローテーションは脳の扁桃体の暴走を抑える!
脳科学的に言うと、理想のローテーションは、できるだけ脳の異なる部分を使う勉強をつなげていくことです。
たとえば、
英単語15分⇒数学15分⇒日本史15分⇒化学15分⇒英語15分⇒数学15分⇒⇒⇒・・・
これだと、文系脳⇒理系脳⇒文系脳・・・になっているので、脳の前頭前野と呼ばれる部分に疲労が溜まりにくいんです。
実は、脳の深い部分にある扁桃体が暴走することで、苦手科目に対する苦手意識が生じます。
そうすると、前頭前野の機能が低下し、集中力・記憶力・思考力が低下します。
これによって、単なる勘違いで苦手科目だと思いこんでいた場合でも、本当に脳はその科目ができなくなってしまいます。
苦手意識は気分だけの問題ではなく、脳がよく働くかどうかにまで影響を与えることだったのです。
この点でも、15分、ローテーションで勉強することで扁桃体の暴走を抑え苦手意識が生まれにくくしておけば、二重に受験にメリットがあるわけです。

扁桃体の暴走は脳医学で抑えられる!
ただし、受験ストレスが一定限度を超えていたり、あるいは「受験うつ」に陥っている場合は、志望校への合格を勝ち取るためには、脳医学の力で扁桃体の暴走を止める必要があります。
特に、合格したい志望校が現在の学力より高い偏差値出会った場合は、なおさら特別な対策が不可欠です。
そこで、私の心療内科クリニックでは、「最新脳医学治療(受験うつ)早期合格コース」を設けました。
以下の3つの専門的な治療法を組み合わせることにより、苦手意識や不安・不満などのネガティブな感情を生み出す扁桃体の暴走を抑えると同時に、集中力や思考力を生み出す前頭前野の機能を高めることで、あこがれの志望校への合格を図ります。
① 受験の脳機能に特化した専門の「磁気刺激治療」
② 受験勉強の方法を変えることにより脳機能を高める「CBT治療」
③ 光トポグラフィー検査のデータを元に、脳機能そのものを高める5つの特別診療
つまり、
「受験専門・磁気刺激治療」+「受験に特化したCBT治療」+「5つの特別診療」=志望校への合格
これが弊院で提唱している「合格の方程式」です!
「最新脳医学治療(受験うつ)早期合格コース」は、短期間でも効果が出やすいという特徴があります。
志望校への合格をあきらめないでください!