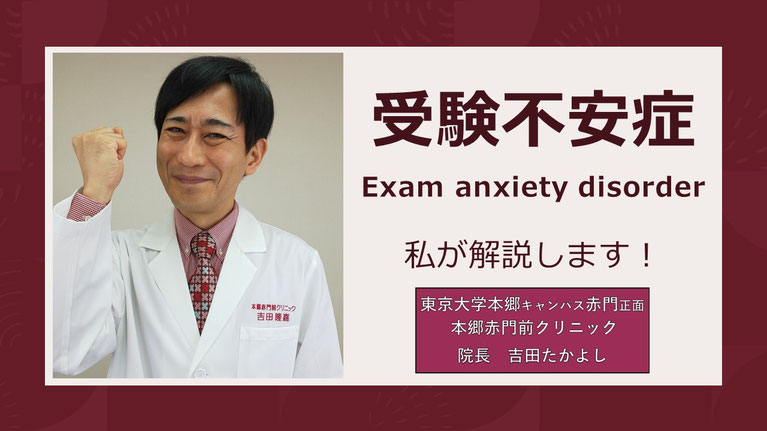受験不安症
Exam anxiety disorder

このページの要点は?
✓ 「受験不安症(Exam anxiety disorder)」とは、入試や勉強に対する不安感が高まり、自分の理性でコントロールができなくなる精神障害です。
✓ 受験に対する精神的ストレスと勉強による脳疲労が脳内で化学反応を起こす結果、「受験不安症」が生じます。
✓ 「受験不安症」を発症すると、脳内で原始的な感情を作り出す扁桃体が過剰に刺激を受けるため、不安感の膨張だけにとどまらず、集中力、ヤル気、思考力など勉強をするための脳の認知機能の低下も生じます。
✓ 一般的な単なる受験や勉強の一過性の不安と、対処が必要な「受験不安症」の見極めが重要です。どなたもセルフチェックができる5か条の一覧表を掲載しています。
✓ 「受験不安症」の場合は、成績悪化が学力の低下によるものではないので、きちんと治療すれば、短期間のうちに成績が大幅に回復し、志望校への合格に直結します。
✓ 志望校への合格を勝ち取るため、ご自分でできる対策も解説します。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

「受験不安症(Exam anxiety disorder)」とは
「受験不安症(Exam anxiety disorder)」とは、受験生が入試や試験に臨む際に過剰な不安や緊張を感じ、それを自分の理性で制御できなくなることが特徴の精神障害です。
受験生自身は集中力を高めて勉強に取り組みたいという意欲を持っているにも関わらず、その意志とは裏腹に、暴走する不安感のために勉強が進まず、それに対する焦燥感から、さらに症状が悪化する傾向があります。
また、「受験不安症」は試験が近づくにつれて悪化し、試験当日には身体的な症状やパニック症状が現れることが一般的です。
試験前には、頭痛、吐き気、嘔吐、めまい、動悸、息切れ、手足の震え、過剰な汗などの身体的な症状が現れることがあります。
また、パニック症状として、不安感や恐怖感、現実感喪失、過呼吸、胸痛、動悸、手足のしびれ感、発汗、吐き気、嘔吐などがあらわれることがあります。
さらに「受験不安症」に罹患している場合、大うつ病性障害や双極性性障害、気分変調性障害などの精神障害を伴う場合も多いので、こちらについての検査も必要になります。
このように、受験生が志望校への合格を勝ち取る上で「受験不安症(Exam anxiety disorder)」は大きな障害となります。
その芽を摘む上でも、普段から受験の不安を膨張させない努力が必要です。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

「受験不安」の暴走が脳機能を蝕む!
受験に対して過剰な不安感を持つことは、合格を勝ち取る上で致命的となるダメージを脳機能に与えます。
「不安で受験勉強に集中できない」と自覚している受験生は多いのですが、問題はそれだけに留まりません。
合格を勝ち取るために最大の障壁となるのは、思考力や創造力など入試の問題を解くために不可欠な脳の働きが低下してしまうことなのです。
人間は不安を感じているとき、脳内にある扁桃体という部分が過剰に刺激を受けています。
その結果、試験問題を解くために必要な能力を脳内で生み出している前頭前野という部分の働きに抑制がかけられるため、自由闊達に物事を考えることができなくなってしまうのです。
こうした症状が一定限度を超えた場合、「受験不安症(Exam anxiety disorder)」に対する適切な治療が必要です。

不安が高まると応用問題が解けなくなる!
脳の前頭前野の機能が悪化すると、以下の能力が低下することが研究で実証されています。
①記銘力(新しいことを覚える力)
②想起力(記憶を思い出す力)
③論理的思考力
④創造力
⑤想像力
⑥集中力
これらの能力は、すべて入試の問題を解くために不可欠なものです。
中でも、特に大きなダメージを受けるのが、応用問題が解けなくなることで、これにより入試に落ちる受験生が毎年、跡を絶ちません。
応用問題は、①記銘力、②想起力、③論理的思考力、④創造力を集中的に使い、さらに⑥集中力によって粘り強く取り組む必要があり、不安による悪影響をモロに受けてしまうわけです。
現在の親の世代が受験生だった頃とは異なり、現在の入試は、応用問題を解く知恵そのものを問う設問が劇的に増加しています。
もし、「受験不安症(Exam anxiety disorder)」に罹患して受験生の精神に不安の暴走が現れたら、現在の入試制度の元では、合格に対して黄色信号、あるいは赤信号が点灯していると考えるべきです。
不安を上手にコントロールしない限り、合格は手に入らない可能性が高いのです。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

受験不安症にひそむ「受験うつ」を見逃さないで!
「受験不安症(Exam anxiety disorder)」に罹患した場合、背後に「受験うつ」がひそんでいる場合が多いので注意が必要です。
実際、「受験うつ」になってしまった方は、例外なく膨張した不安感に苦しみます。
受験不安のコントロールを目的に当院を受診されたことがキッカケで「大うつ病性障害」や「双極性性障害」、「気分変調性障害」など、「受験うつ」が見つかったケースは、とても多いのです。
もちろん、この場合は、すみやかに適切な治療を施すことが必要です。
また、仮に、うつ病の診断基準は満たさなかったとしても、膨張した不安に苦しむ受験生の多くが、うつ病に類似した状態に脳機能が陥っています。
この場合も、確実に合格を手にするためには、脳機能が抱える問題点に対し「受験うつ」としてうつ病に準じた対処を行うことが必要なのです。
心の底から沸き上がってくる不安感は、いわば脳が発するSOSサインです。
大切なSOSサインを見逃してしまったら、受験生を救出することは永久に不可能です。

正常な「受験不安」と異常な「受験不安症」の境界線とは?
専門の治療が必要な「受験不安症(Exam anxiety disorder)」と、そうではない不安の見極めは、とても重要です。
多くの受験生やご家族は、「受験生なんて、不安なのが当たり前だ」と不安の暴走を甘く見てしまうようです。
もちろん、正常な「受験不安」は、勉強を促してくれるのでプラスに作用します。
ただし、その背後には、「受験うつ」による不安や不合格に直結する危険な「受験不安症」が潜んでいる場合が多いのです。
以下に、見逃してはいけない危険な症状のリストを示しておきます。
受験生やご家族の方は、該当する項目がないか、チェックしてください。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

「受験不安症」のセルフチェック5か条!
以下の症状が、2週間以上続く場合は、脳機能のSOSサインとして、適切な対処が必要な危険な「受験不安」です。
まずは、受験勉強に関する脳機能について、専門の検査をお受けになることをおすすめします。
① 各科目や各分野が次々に不安になり、勉強の内容をコロコロと変えてしまって、結果として受験勉強がはかどらない。
② 覚えたはずなのに忘れるような気がして、同じことを何度も繰り返し勉強してしまい、受験勉強がは先に進まない。
③ 教科書を読んでいるとき、不安で集中できず、前のページに何が書かれていたいたかも思い出せないことがある。
④ 以前は解けたはずの問題が不安感のために解けなくなってしまう。あるいは、覚えているはずのことまで思い出せなくなる。
⑤ 本当は家族のことを大切に思っているのに、受験に対する不安から、悪態をついたり、わめいたり、場合によっては暴力を振るったりしてしまう。
この他、入眠困難(寝付きが悪い)、中途覚醒(夜中に目が覚める)、早朝覚醒(十分に睡眠がとれていないのに目が覚める)といった症状も見逃してはいけません。

ご自分でできる不安の対策は?
メンタル医学の研究で、適度な運動を行うことが、試験に対する不安感の軽減に役立つことがわかってきました。
たとえば、医学部生は、世界各国のどこでも厳しい試験にさらされており、試験に対する不安はとても大きい集団ですが、普段から運動をしている医学部生は、試験に対する不安感が生じにくいというデータが出ています。
Factors causing exam anxiety in medical students.
Published in JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association
中でも、縄跳びはその効果が高く、受験生には特におすすめです!
また、認知の歪みを治すと、不安感の暴走が抑えられるという研究が発表されています。
不安感を和らげるポーズも、メンタル医学の研究で解明されています!
ただし、以上は、一般的な入試に対する不安感の軽減には役立ちますが、「受験不安症」を発症している場合は、以下の専門的な治療が不可欠です。
東京大学本郷キャンパス赤門正面
本郷赤門前クリニック

「受験不安症」の最新治療とは?
当院では、まず、受験に特化した光トポグラフィー検査を行い、「受験不安」を感じる場合、脳のどの領域がどのような活動をしているのが、性格にデータ化します。
それをもとに、「受験不安」の本質的な原因を、脳機能医学の面から解明します。
さらに、必要があれば、磁気刺激治療によって、機能不全を起こしている脳の領域の活動を正常化させるとともに、脳機能にピッタリ合った受験勉強の方法をデザインします。
また、以下の集中力アップ特別診療も、「受験不安」を抱える方が志望校への合格を勝ち取る上で、大きな効果を発揮します。


集中力アップ特別診療で得点力アップ!
受験生の脳機能や認知機能を検査し、そのデータに合わせて勉強法などを見直すことにより、不安の暴走を止め、かつ、脳の働きを高めて大幅な得点力アップが可能となります。
弊院では15年前から、こうした診療を重視してきましたが、2020年10月より診療プログラムを再編し、「5つの特別診療」という診療プログラムを導入しました。
これは、以下の5種類の特別診療の中から、受験パニックに関する検査データをもとに、志望校への合格に大きな効果が見込める専門の診療を選択して受けていただくものです。
受験不安の場合は、脳内の扁桃体が過剰に刺激を受けているために、集中力のコントロールができなくなっている場合が多く、このようなケースでは「②集中力アップ特別診療」がとりわけ効果的です。
また、受験不安が悪化すると、知っていることを思い出せなくなる、いわゆる「ど忘れ」をしてしまう受験生も多いのですが、このような場合は「④記憶力アップ特別診療」が大きな力を発揮します。
以下をクリックしていただけば、「5つの特別診療」に関する詳しい案内がご覧いただけます。